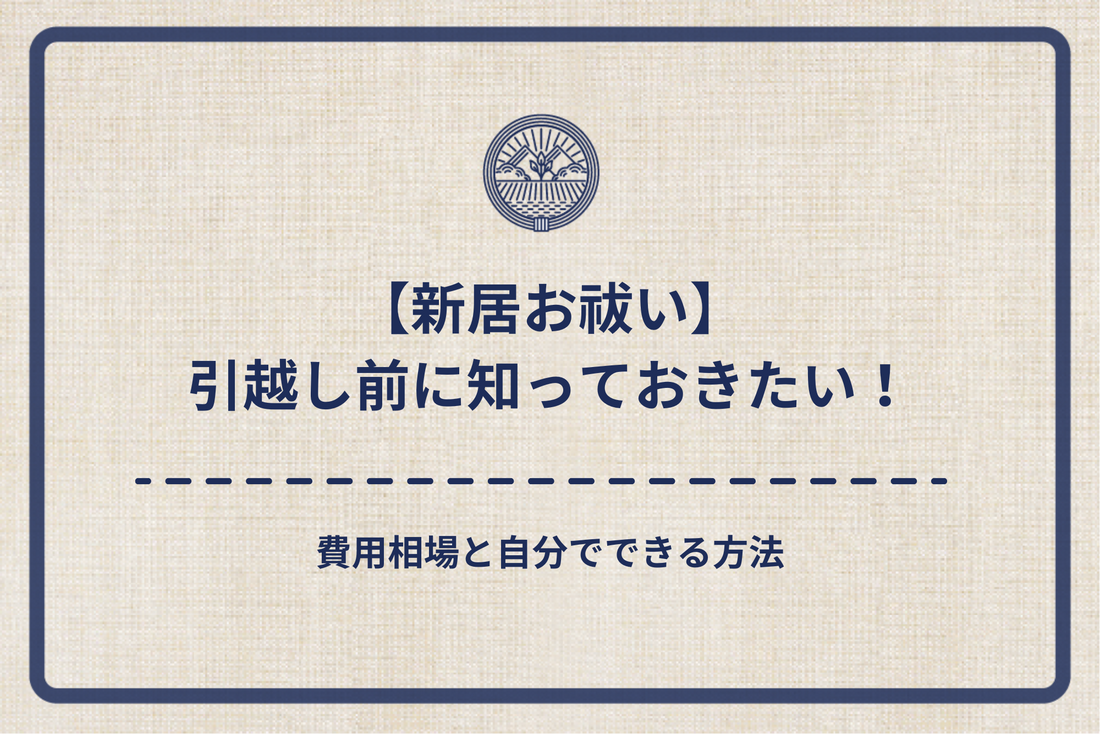新居のお祓いは、住まいの邪気を払い、これからの暮らしの安全と幸福を祈願する大切な儀式です。しかし「費用はどれくらいかかるの?」「自分でもできるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、依頼する場合の費用相場から、自分でできるお清め方法まで、新居お祓いについてわかりやすく解説します。引越しシーズンを迎える前に、あなたの新生活を清々しくスタートさせるための知識を身につけましょう。

新居お祓いとは?その意味と重要性
新居お祓いとは、新しい住まいに入居する際に行われる神道の儀式です。この儀式には「邪気を祓い、安全を願う」という重要な意味があります。
お祓いの主な目的は以下の3つです。
・住まいに宿る不浄や邪気を取り除く
・家族の安全と健康を祈願する
・新生活の幸せな門出を祝福する
日本の伝統では、新しい空間には様々なエネルギーが存在すると考えられています。お祓いのベストなタイミングは入居前です。
家具や荷物が入る前に行うと、空間全体を清められます。神道の考えでは、清らかな状態から新生活を始めると、家族の繁栄と幸福につながるとされています。
関連記事:新居入居前にやることリスト!快適な新生活スタートのための準備
新居お祓いの費用相場
新居のお祓い費用は依頼先や地域によって異なります。詳しく見ていきましょう。
神社で依頼する場合の料金相場
神社に新居のお祓いを依頼する場合、一般的に「玉串料」や「初穂料」と呼ばれる礼金が必要になります。料金相場は以下のようになっています。
◾️マンションや一般住宅の場合
・一般的な相場:20,000円~50,000円
・大都市圏の有名神社:30,000円~80,000円
・地方の中小神社:10,000円~30,000円
お祓いの料金には、神主さんへの謝礼だけでなく、お供え物や祭具の費用も含まれる場合があるでしょう。事前に神社に確認してください。
寺院で依頼する場合の料金相場
寺院に新居のお祓いを依頼する場合、一般的に「読経料」や「お布施」という形で料金をお支払いします。平均的な相場は20,000円~50,000円程度となっています。
費用の内訳は主に以下の通りです。
・基本読経料:15,000円~30,000円
・お供え物代:3,000円~10,000円
菩提寺や檀家になっているお寺であれば、特別料金が適用される場合もあるでしょう。また、地域によって料金体系が異なり、都市部では比較的高額になる傾向があります。
出張お祓いを依頼する場合の費用
出張お祓いは、神職や僧侶が直接新居に来てくれるため、忙しい方や移動が困難な方に便利なサービスです。費用は依頼先や地域によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
◾️出張お祓いの一般的な費用相場
・個人住宅の場合:20,000円〜30,000円
・マンション/アパートの場合:15,000円〜25,000円
・事務所/店舗の場合:30,000円〜50,000円
なお、上記金額に加えて以下の追加費用が発生する場合があります。
【追加で発生する可能性のある費用】
・交通費:神社から片道10km以上の場合に発生(実費)
・お供え物/道具代:約10,000円前後(神社側で準備する場合)
・日程指定料:土日祝や早朝/夜間の場合(5,000円〜10,000円増)
事前に見積もりを取るのをおすすめします。また、複数の部屋や広い物件の場合は追加料金が発生する場合もあるため、依頼前に詳細を確認しておくと安心です。
地域差と季節変動について
新居のお祓い費用は、地域や時期によって変動するケースもあります。特に地域差については、都市部と地方で以下のような違いが見られます。
【地域による費用差】
都市部:30,000円〜50,000円が一般的
地方:20,000円〜40,000円程度が多い傾向
さらに、季節による変動も見逃せません。引越しシーズンとされる3月〜4月や、土用の期間は特に注意が必要です。
避けるべき時期として「土用期間」があります。土の動きが盛んなため工事に不向きで、費用もやや高くなる傾向です。また「三隣亡の日」は建築に大凶とされ、予約が取りにくくなります。
地域によっては、お祓いの際に準備する神饌(お供え物)の内容や盛り塩の作法にも違いがあります。事前に依頼先に確認しておくと安心です。
なお、神社によっては繁忙期に出張料が割増になる場合もありますので、余裕をもって予約しましょう。
関連記事:新築内祝いの相場やタイミングとは?「のし」の選び方や書き方、注意点まで徹底解説!
自分でできる新居お清めの4つの方法
新居のお清めは自分でも行えます。伝統的な方法から現代風のアレンジまで、ご自身で実践できる4つの方法をご紹介します。
1.盛り塩によるお清め方法とコツ
盛り塩は最も一般的なお清め方法です。白い紙を敷いた小皿の上に天然塩や粗塩を山形に盛ります。塩が形を保ちにくい場合は、霧吹きで軽く湿らせると固まりやすくなります。
効果的な場所は玄関や各部屋の四隅です。お清め後は1〜3時間で撤去し、トイレに流すか燃えるゴミで処分しましょう。
2.お神酒を使ったお清めの手順
お神酒(おみき)は新居の浄化に使われる伝統的な方法です。清酒と盃、布巾を用意し、玄関から時計回りに各部屋の四隅へ少量ずつ撒きます。
特に水回りは重点的に行い、布巾で軽く拭き取ります。引越し当日、搬入前後に行うのが理想で、夕方〜夜に実施すると効果的です。「穢れを祓い、清めます」と唱えるとより良く、最後に玄関先に残りのお神酒を撒くと締まりが良いとされています。
3.塩と酒以外の伝統的なお清め方法
盛り塩やお神酒以外にも、日本には様々なお清めの方法があります。例えば、玄関に柊や柚子を飾ると邪気を払うとされ、特に柊のトゲは魔除けの力があると信じられています。
青竹や笹を玄関や庭に置くのも清浄な気を呼び込む方法です。また、白檀などの香木や線香を焚いて空間を浄化するのも効果的です。
さらに、塩水で家の四隅や玄関を拭く方法も簡単に実践できます。地域の風習も参考にするとより良いでしょう。
4.現代風アレンジ:アロマやハーブを使った空間浄化
伝統的なお清めに加え、現代ではアロマやハーブを使った空間浄化も人気です。ティーツリーは強力な抗菌作用があり、ラベンダーは新生活のストレス緩和に、レモングラスは爽やかな浄化に適しています。
セージの燻煙やローズマリーのポプリ、ユーカリ水での拭き掃除も効果的です。取り入れる際はアレルギーやペットへの配慮も大切です。
伝統と現代の方法を組み合わせると、より心地よい空間づくりが可能になります。
関連記事:【新居の掃除】入居前掃除ガイド!手順・場所・便利グッズまとめ
こだわりギフト専門店「晴日和松吉商店(はれきち)」のご紹介

こだわりギフト専門店「晴日和松吉商店(はれきち)」では、瀬戸内地方で厳選した「きぬむすめ」や「こしひかり」などのお米をオリジナルのギフトパッケージにて販売しております。パッケージデザインは、シンプルながらも、洗練されたモダンなデザインが人気です。
また、パッケージは9種類あり、用途や贈る相手に合わせてデザインを選択できます。さらに、名入れのオプションサービスや急ぎの注文にも対応しています。⇒こだわりギフト専門店「晴日和松吉商店(はれきち)」
新居お祓いでよくある質問3つ
新居のお祓いを依頼する際に、多くの方が疑問に感じるポイントを3つにまとめました。
質問1.お祓いを受けた後、家に神棚や仏壇を設置する必要はありますか?
お祓い後の神棚や仏壇の設置は必須ではありませんが、お祓いの効果を持続させる一つの方法とされています。設置する場合は、方角(神棚は南向き、仏壇は北向きが基本)や高さ(目線より高い位置)に配慮しましょう。
スペースや生活スタイルに合わない場合は、小さな置き型の神棚や、写真立てサイズの仏壇など、現代の住環境に合わせたコンパクトなものも販売されています。
質問2.お祓い後、家に置いてはいけないものや避けるべき行動はありますか?
お祓い後は、古い時計(特に止まっているもの)、割れた鏡、使わない電化製品など「滞った気」を生みやすいものは避けるとよいとされます。また、お祓い直後の3日間は大掃除や大きな模様替えを控え、清められた空間を落ち着かせるのが望ましいとされています。
入居後1週間は、できるだけ来客を控えて家族だけで過ごすという考え方もあります。
質問3.新居お祓いと厄払いを同時に行えますか?
可能です。多くの神社やお寺では、新居のお祓いと個人の厄払いを同時に執り行うプランを用意しています。特に引越しと厄年が重なる場合や、家族に厄年を迎える人がいる場合は、同時に行うと、時間と費用の節約になります。
ただし、同時に行う場合は、通常より費用が高くなったり、準備に時間がかかったりする場合を考慮してください。
まとめ
本記事では、新居お祓いの意味や重要性から、神社・寺院での依頼費用、出張お祓いの相場まで幅広く解説しました。また、盛り塩やお神酒を使った自分でできるお清め方法や、アロマやハーブを活用した現代風の空間浄化方法もご紹介しました。
新居お祓いは古来から日本人が大切にしてきた習慣であり、新しい住まいで心地よく暮らすための大切な儀式です。あなたとご家族にとって最適な新居お祓いの方法を選び、安心して新しい生活を始められることを願っています。
なお、こだわりギフト専門店「晴日和松吉商店(はれきち)」では、瀬戸内地方(主に岡山県、香川県、愛媛県)の厳選した安心・安全なオーガニック商品をオリジナルのギフトパッケージにて販売しております。名入れのオプションサービスも提供していますので、ぜひご利用ください。⇒こだわりギフト専門店「晴日和松吉商店(はれきち)」